病棟で退院支援をしているときに

自宅で両親の介護をするのは良いけど
自分も仕事をしていて忙しいから
できるだけ多くのサービスを利用したいけど
どうしたらいいの?
なんていう相談をされたことがある方も多いのではないでしょうか
通常、介護サービスを利用しようとするときには
介護度に合わせて地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にケアマネージャーを依頼し
デイサービスは「〇〇事業所」、ヘルパーは「△△ヘルパー事業所」、ショートステイは「◇◇ホーム」、福祉用具は「☆☆事業所」といった感じで、利用を希望する各サービス事業所とそれぞれ契約し
患者さん・ご家族の希望に合わせてそれぞれ何をどのくらいの頻度で利用するかを相談・検討し……
といった感じで、サービス内容を調整をしていきます
この場合

「◇◇ヘルパー事業所」のスタッフややり方が自分たちに合わないから
他の事業所に変更してほしい
なんていう患者さん・ご家族の意向に合わせて
柔軟にサービス提供事業所やサービス利用量を変更・調整できるメリットもありますが
その一方で、サービスを使ったら使った分だけ費用は掛かります
そのため、なるべく多くサービス利用を希望する場合は
介護保険支給限度額を超えてしまい、自費が発生してしまうこともありますし
希望した量のサービスを利用できないことも多くあります
そのため、なるべく多いサービスを柔軟に利用したい希望がある場合には
「小規模多機能型居宅介護」
の利用も選択肢に入れるとよいでしょう
先ほど説明した、通常の介護サービスの利用時とは特徴やメリット・デメリットが異なる介護サービスの利用方法になるのですが
普通にケアマネージャーを頼む時と何が違うのか?
わからない方も多くいるかと思うので、この記事でご紹介していこうと思います♪
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは?
利用者ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、利用者の希望や選択に合わせて
- 施設への「通い(デイサービス)」
- 短期間の「宿泊(ショートステイ)」
- 利用者の自宅への「訪問(ホームヘルプサービス)」
の3つを組み合せ、住み慣れた街で日常生活の支援や機能訓練を受けることができます
このような、通い、訪問、宿泊サービスを一つの事業所が提供するのが
「小規模多機能型居宅介護」の特徴です

認知症の方など
環境や関わる人の変化が苦手な方でも
同じ事業所の顔なじみのスタッフからサービス提供を受けらるのが安心ですね

通い・訪問・宿泊以外に
「福祉用具」や「訪問看護」「訪問診療」などを利用する場合は
別の事業所のサービスを利用することになります
サービス提供エリアは?
小規模多機能型居宅介護は「地域密着型サービス」に位置付けられています
「地域密着型サービス」の場合、お住まいの住所と事業所の住所が、同じ市区町村になければ利用できません
そのため、住所地に利用できる「小規模多機能型居宅介護事業所」があるかどうかは確認が必要です

同じ市区町村内にあっても、自宅が事業所から遠いと施設車での送迎を対応できないこととかもあるみたいです
少し遠方の事業所の利用を希望するときには一度確認してみましょう!
利用料は?
介護度に合わせてサービス利用料は異なります(1割負担の場合)
| 介護度 | 1か月の利用者負担(1割負担) | |
|---|---|---|
| 同一建物に居住する者以外 | 同一建物に居住する者 | |
| 要支援1 | 3,403円 | 3,066円 |
| 要支援2 | 6,877円 | 6,196円 |
| 要介護1 | 10,320円 | 9,298円 |
| 要介護2 | 15,167円 | 13,665円 |
| 要介護3 | 22,062円 | 19,878円 |
| 要介護4 | 24,350円 | 21,939円 |
| 要介護5 | 26,849円 | 24,191円 |
※引用:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 小規模多機能型居宅介護」
この利用料の他に、日常生活費(食費・宿泊費・おむつ代など)が別途かかります

[通い][訪問][宿泊]のサービスをどれだけ使っても
介護サービスの利用料が一定なのは安心ですね

逆に言うと
あまり[通い][訪問][宿泊]のサービスの利用を希望しない場合は
逆に高くついてしてしまう可能性もあるので要注意です
サービスの利用回数の制限は?
基本的には、24時間365日サービスの利用が可能で、特に法律上の回数制限はありません
ですが、各定員の決まりはあります
| 1事業所あたりの登録人数 | 29人以下 |
| [通い]サービスの定員(1日あたり) | 15人以下 ※所定の要件を満たすと18人以下 |
| [宿泊]サービスの定員(1日あたり) | 9人以下 |
このため、他の利用者さんとの兼ね合いで、利用回数に制限が出てくることはあるので注意が必要です

回数制限がないからって、好きなだけ利用ができるわけではないんですね

小規模ゆえに人数制限はありますが
その分きめ細やかなサービスを受けることができますよ
職員配置
小規模多機能型居宅介護で必要な職員配置は以下の通りです
| 代表者 | 「認知症対応型サービス事業開設者研修」を終了した者 | ||
|---|---|---|---|
| 管理者 | 「認知症対応型サービス事業管理者研修」を終了した常勤・専従の者 | ||
| ケアマネージャー | 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を終了した者1人以上 | ||
| 小規模多機能型居宅介護従業者 | 日中 | 通い | 利用者3人に対して1人以上 |
| 訪問 | 1人以上 | ||
| 夜間 | 夜勤職員 | 1人以上 | |
| 宿直職員 | 1人以上 | ||
| 看護職員 | 1人以上 | ||
※引用:厚生労働省【小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(参考資料)】

小規模多機能型居宅介護では、ケアマネージャーも同一事業内にいて
利用者さんに合わせたケアプランを作成してくれます

看護師も、主に日中にいるため
利用者さんの体調管理などを行っています

小規模多機能型居宅介護の看護師がどこまでの医療処置を行えるかは
各事業所によって少しずつ異なるため
膀胱留置カテーテルやインスリンなど何らかの医療処置が必要な場合は
対応可否を利用を希望する事業所に確認してみてくださいね
メリット
24時間365日利用回数の制限なく利用することができる
利用定員を守れば、利用回数の制限はないのは大きなメリットです

急な出張が入って
どうしても明日から宿泊を利用したい

夜中なんだけど
利用者が部屋で転んじゃってて1人で起こしたり対応するの難しい
いまから訪問に来て手伝ってほしい
なんて時にも、利用定員に空きがあれば利用相談が可能です
本人・家族の生活状況や体調に合わせて柔軟にサービスを利用することができるのは、小規模多機能型居宅介護の大きな強みです
月額定額制
通常、介護サービスは利用すればしただけ料金がかかるため
複数サービスを頻回に利用する場合は介護保険支給限度基準額を超えてしまい
自己負担分が発生してしまうことがあります
一方、小規模多機能型居宅介護では
どんなにサービスを利用しても月額料金が一定のため
介護保険支給限度基準額からはみ出す心配がないのは安心です

介護保険支給限度基準額を超えた分は、「全額自己負担」になってしまいます

どれだけサービスを利用しても、介護保険支給限度基準額を超えないというのは安心ですね
1つの契約で複数の介護サービスを利用できる
通常、ケアマネージャーや福祉用具、デイサービスなど、利用する介護サービスの数だけ契約をする必要があります
しかし、小規模多機能型居宅介護の場合は、1つの契約で複数の介護サービスを利用できます
複数の契約を結ぶというのは意外と手間と労力がかかるため、その負担を減らせるというのもメリットの1つです
同じスタッフが通い・訪問・宿泊のサービスを提供してくれる
自分をよく知る同じスタッフが、通い・訪問・宿泊のサービスを提供してくれるため
環境や人の変化に弱い方にはとっても安心です
また、すべてのサービスが同一事業内にあるため
スムーズな連携や情報共有をしてくれるもの安心感があり、メリットといえるでしょう
デメリット
併用できるサービスに限りがある
これまで利用していたサービスでも、小規模多機能居宅介護で提供できるサービスは利用できなくなります
| 併用できる | 併用できない |
|---|---|
| 訪問看護 | 居宅介護支援 |
| 訪問リハビリテーション | 訪問介護 |
| 福祉用具 | 訪問入浴 |
| 住宅改修 | デイケア |
| 居宅療養管理指導 | デイサービス |
| ショートステイ |
また、小規模多機能型居宅介護では様々なサービスを提供できるようにするため、介護保険支給限度基準額の大半の単位を使用します
そのため、併用できるサービスであったとしても、介護保険支給限度基準額内で利用しようとした場合、大きな制限がかかってしまいます

介護度と、どれだけ追加のサービスが必要かにもよりますが
自宅の福祉用具を整えただけで、介護保険支給限度基準額の残りの単位を使い切ってしまうこともあります

もし追加で訪問看護・訪問リハビリの利用を希望する場合
毎週利用する代わりに時間を短くしたり自己負担額が発生してしまうか
単位内で利用するために利用頻度を隔週等に調整するなど
何らかの調整・相談が必要になることが多いです

小規模多機能型居宅介護のサービス以外の利用を希望するときには
ケアマネージャーとよく相談してみてくださいね
サービス利用頻度によっては逆に高くつくことがある
小規模多機能型居宅介護のサービスをたくさん利用しても、全く利用しなくても、利用料金は毎月一定です
そのため、週に1~2回しかサービスを利用しないなど、サービス利用回数が少ない場合は逆に料金が高くなってしまいます

毎日サービスの利用が必須!とかではなく
週数回のデイサービスやヘルパーのみ、という場合は
通常通りケアマネージャーに必要な量だけサービス提供をしてもらった方がよいこともあるので
病院の退院調整看護師やMSW、地域包括支援センターの人に相談してみてくださいね
小規模多機能型居宅介護のサービスの一部のみ別の事業所を利用することはできない
自宅療養をしていてよくあるのが

ケアマネージャーが自分と合わないから、ほかの事業所の人に変えてほしい

もっとリハビリができるデイサービスを利用したいから
などの、他の事業所への変更相談です
通常のケアマネージャーを利用してのサービス調整であれば、こういった相談・調整は簡単に行えますが
小規模多機能型居宅介護の場合、すべてのサービスが同一事業内にあり、類似のサービスは併用できないため、一部のみ変更は受け付けられません
もしどうしても変更したい場合は、ケアマネも各サービスもすべて変更するしかないのです

小規模多機能型居宅介護のサービスが万が一合わなかったときは
すべての契約解除になってしまうので
また一からすべてを調整することになってしまい、大変ですね
介護サービス利用料とは別に、日常生活費が発生する
「通い」「宿泊」「訪問」の介護サービスは月額定額で利用できますが
それに付随して発生する、食費や宿泊費、おむつ代、おやつ代などの日常生活費は別途発生します
そのため
①利用したいサービスの内容・頻度
②サービス利用料 + 日常生活費(食費・宿泊費・おむつ代など)の総額
この①と②の両方の希望・条件を確認し
実際どのサービスをどの程度まで利用できるのか自分たちの限界値を知っておくことが大切です

宿泊サービスを利用しすぎて
あっという間に10万/月以上になっちゃった!
という人も過去にいましたよ

月額定額だからといって油断は禁物ですね…

担当ケアマネージャーとそのあたりは事前にしっかり確認・相談しておきましょうね
利用方法
要介護認定を受けていることが第一条件となります
そのため、まずは区役所や地域包括支援センターへ行き、要介護認定の申請をしましょう
要介護認定がおりて、「要支援」「要介護」になった場合、利用が可能です
利用を希望する場合は
もともとケアマネージャーがついている場合は、ケアマネージャーにまずは相談をしましょう
これまでケアマネージャーがついていなかった場合は下記に相談してみてくださいね
- 病院の退院調整看護師やMSW(入院中の場合)
- 役所
- 地域包括支援センター
- 小規模多機能多機能型居宅介護事業所
最後に
主介護者が仕事で忙しかったり、本人の体調が不安定でたくさん介護サービスの利用を希望する方にとって強い味方となる「小規模多機能型居宅介護」
より安心、安全に、無理なく在宅療養を続けていくための選択肢として、患者さん・ご家族だけではなく病院スタッフもぜひ「小規模多機能型居宅介護」について知っておいてくださいね
また、同じようなサービスを提供するもので「看護小規模多機能型居宅介護」というものもあります
こちらの記事もぜひ参考にしてみてくださいね♪
そしてそして、「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」の違いについてもまとめてみたので、ぜひ見てみてくださいね♪
ではまた!
参考文献
厚生労働省のページを参考にしています
よければ見てみてくださいね
在宅療養関連の記事
これまで、在宅療養関連でこのような記事も書いています
ぜひ見てみてくださいね♪


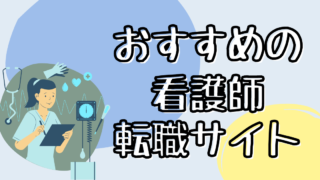
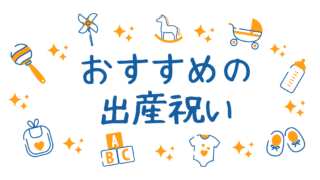


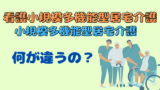




コメント