現在、国が入退院支援に力を入れていることもあり、「退院調整看護師」がいる病院が増えてきました
退院調整看護師は、患者さんやご家族が、自宅や施設等に帰っても、必要な治療やケア、看護・介護を切れ目なく、スムーズに受けることができるように各種調整をしていきます
そして、同じように患者さん・ご家族への退院調整業務を担っている業種といえば、医療ソーシャルワーカー(MSW)もいます
退院調整看護師と医療ソーシャルワーカーは、似たような役割を担い、似たような支援をしているように見えますが、
得意な側面が異なるため、役割分担をしながら連携して仕事をしています
とはいえ、

同じ部署にいることが多いし
同じような退院業務を担って支援をしていることも多いから
一緒に働いていてもよく違いが判らないよ~?
なんて話をよく聞くので
その得意な側面や、役割分担についてご紹介していきたいとおもいます
退院調整看護師と医療ソーシャルワーカーの違い
退院調整看護師も、医療ソーシャルワーカーも、患者さんや家族、介護者の思いや希望を受け止め、その人らしく生きるサポートをしていることは変わりません
また、退院調整を担当しているという意味では、同じ方向を向いて働いています
とはいえ、
退院調整看護師は【医療職】
医療ソーシャルワーカーは【福祉職】
専門性の違いから
得意な部分や
退院支援を行っていくときの視点、重点を置く場所が異なります
退院調整看護師の役割
退院調整看護師は、
患者さん・ご家族が、自宅での療養生活を行うにあたって必要な退院調整・支援
を行うのが主な役割です
退院調整看護師として働く人の多くは、10年以上の臨床経験のある看護師です
もともと看護師として働いてきていることから
医療や看護・介護についての高い専門性・技術・知識・経験があります
また、患者さん・ご家族についての情報を把握するときの視点も
身体状況や疾病など、医療的側面から確認する傾向が強いです
そのため、自宅での看護や介護について、専門的なアドバイスが行うことできるのが特徴です
また、医療的な知識・経験があることで、訪問診療医や訪問看護師と、より密に連携・情報共有が行えます
そのため、医療必要度の高い状態(呼吸器、CV、吸引、褥瘡などの医療処置がある状態)で退院し、自宅療養をする予定の方は
退院調整看護師が担当することで、より切れ目のない、スムーズな在宅療養への支援が行えることが多いです
医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカーは、病院で働く福祉職です
福祉職という特徴から、社会的な生活が送れるように患者のサポートを行うことに重点を置いて退院調整業務を行う傾向があります
医療ソーシャルワーカーの場合、行政や保険、福祉に関するより専門的な知識を持っています
退院後に身体的な介護が必要なのに介護保険を持っていない、金銭的に不安がある、老々介護など介護環境・生活面の心配がある、といった社会的な問題を抱えている方へのアドバイスや関係各所との連携・調整は医療ソーシャルワーカーの方が優れているでしょう
そのため、自宅退院だけではなく、転院や施設入居調整等が必要な方は、医療ソーシャルワーカーが退院調整を担う場合が多くなります
退院調整看護師と医療ソーシャルワーカーのどちらがどの程度、どんな役割を担うかは、
各病院の規模や配置人数、患者層などによっても異なってきます
私が働いている職場では、大まかには上記のような役割分担をしていますが、
明確に分けることはなく、退院調整看護師と医療ソーシャルワーカーが一緒になって連携・調整しながら退院調整業務を担っているようです
他の病院では、転院や施設調整は医療ソーシャルワーカー、在宅に帰る場合のみ退院調整看護師、など退院先が決まった時点で明確に分担しているところもあります
最後に
自宅に帰る場合も、施設等に退院する場合も
在宅領域にいる、クリニックや訪問看護などの医療職者、ケアマネ・ヘルパーなどの福祉職者、行政機関、民生委員などの地域の社会資源などなど、地域にある多くの組織や関係者との協働が必要不可欠です
また、院内でも医師や看護師、セラピスト、栄養科など各職種と退院に向けた協働が必須です
そんな、退院調整業務の中心となる退院調整看護師と医療ソーシャルワーカーは、それぞれの得意分野を生かしながらも助け合い、連携をとっていくことが大切です
お互いの役割を把握し、助け合いながら働いていけるとよいのではないかと思います
退院調整看護師やMSWが行う、退院支援・退院調整の違いって何?という方はこちらの記事をご参考ください
ではまた!


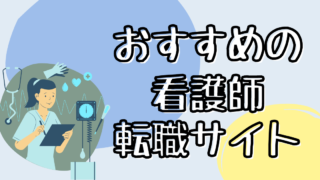
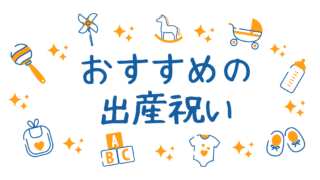




コメント